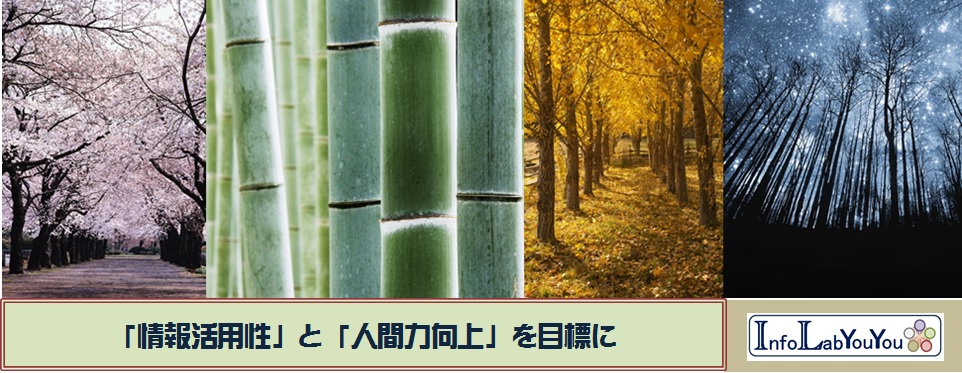”インフオラボ游悠"のホームページへようこそ! (「インフオラボ游悠」およびロゴマークは、本サイト作成者による登録商標です)
インフオラボ游悠(ゆうゆう)は、ビジネス目標達成を目指す「ご縁のある」企業様や各種団体様への、「ビジネス戦略実行とデータ利活用の視点」で、ご提案・ご支援実施を目的に活動しています。
このサイトでは、当研究所の活動全般に関するご案内や、メッセージ発信をしてゆきます。(プロフィールは、こちら)
また、必要に応じた文化活動などにも関わって行きたいと考えており、そういった関連情報も提供する予定です。
(貴サイトからのリンクを希望する場合、当ページをリンク下さい。またリンク時実施時はお問い合わせ経由でお知らせ下さい)
以下の「游悠レポート」お役立ちサイトも併せて参照下さい。面白い話題が見つかるでしょう。
データマネジメント、データウェアハウスとBI、データサイエンス領域でのご興味のある方は、「お問い合わせページ」から所長宛
ご連絡下さい。尚、これまでの標準的なサービスの提供は一旦休止させて頂いております(2023年5月31日より)。
(2025年11月27日更新済)資料類は、上の「游悠レポートサイト」ボタンをクリックしてダウンロードページへ進んで下さい。
【所長の視点】
その158: データサイエンティスト協会発行のスキルチェック・リストについて

この欄で以前内容について触れたことのあるデータサイエンス協会発行の「データサイエンスティスト・スキルチェックリスト」のVersion 6.00の初版が、2025年12月1日に発表されました。今回の特徴として筆者が捉えたのが、昨今のAI技術利用の広がりを見据えて、AIの運用・応用に当たる領域として1段立体的にスキルセットを位置づけた「融合」分野が加わった点でした。この融合分野の中に、この欄でもここのところ集中して検討・説明している「オントロジー」というスキルカテゴリが明示的に設けられた点に、特に着目しました。今回は、このオントロジー分類カテゴリに記述された13項目を中心に、筆者の観点からの検討意見を記述しておきたいと考えています。
その「オントロジー」分類カテゴリは「融合」分野の中で「AI実装・運用」分類の中の8種類のスキルカテゴリの中の1つとして整理されています。習得要求程度は全て「選択」項目扱いです。更に「オントロジー」カテゴリの中の13項目は、「オントロジー設計」(5項目)、「ナレッジグラフ構築」(5項目)、「セマンティック解析・推論」(3項目)の3つのサブカテゴリに分けられています。以下の説明では、スキル項目の内容は記載せず、項目番号だけで参照します。具体的項目内容について興味のある方は、データサイエンティスト協会のWebページからダウンロードして確認下さい(注1)。
前述のように分類「AI実装・運用」のスキルカテゴリ「オントロジー」でのスキル項目は13個あります。そのサブカテゴリ「オントロジー設計」では5項目記述があります。項目Sub
No.1、2では、オントロジー体系設計について構造化設計を挙げていますが、筆者としてはこれらの内容は、これまでの関係性モデル作成で行っていた内容に該当する内容であり、ER図やUML/クラス図表現としての関係性データモデル化のスキル領域に分類する方が適切であると考えます。関係性データモデルと最近のセマンティックWeb系統から来るオントロジー設計と呼ぶ方法はアプローチに違いがあり、設計への視点の差異があります。この意味でオントロジー設計項目分類とは切り離す方が、広い意味で技術者に分かり易いだろうと考えます。ここで筆者の云う両者のアプローチの違いについては、別途の機会で説明したいと考えます。Sub
No.3は、AI推論に関する具体的内容が示される必要があるでしょう。何故ならここでのオントロジー設計は集合論理に基づく推論支援として考えられるものだからです。Sub
No.4は、「文化的・価値観的バイアスを特定した緩和策」の具体的イメージを語ることが必要でしょう。Sub No.5は、グラフRAGアプローチの内容の応用を語っているように見えます。そのような表現の方が理解しやすいのではないでしょうか。
次に「ナレッジグラフ構築」サブカテゴリにある5項目です。Sub No.6は、No.5と同様グラフRAGに関係している(こちらは構築に関するスキル)。No.7は、セマンティック解析・推論の初歩のスキルに相当する。No.8は、やはりRAGに関係する内容。No.9は、「オントロジーを含めて動的に更新する」という意味であれば、オントロジーが動的に変化してしまうことは足下の構造が常に変わる可能性を示し、生み出される回答の不確定性を高めるという点で、もっと説明が必要でしょう。No.10は、セマンティック解析・推論に関わる実装スキルに見えます。その点で詳細化・具体化が必要でしょう。
「サブカテゴリ/セマンティック解析・推論」のSub No.11~13の項目の項目記述を見ると、必ずしも「オントロジーというスキルカテゴリの中に含めるべき項目とは合致している訳ではないのでは?」と筆者は感じました。「セマンティック解析・推論」というカテゴリ名は、例えばスキルカテゴリに「セマンテック」を加えた上で、その中の「スキルカテゴリ「(セマンティック)解析・推論」というサブカテゴリ以上の上位カテゴリとして表現する方が妥当なのではないかと考えます。
このスキルチェックリストは発行されたばかりであり、今後改訂や記述される説明を具体化、詳細化する内容が追加されるものと期待されます。現時点の筆者からの意見として関係者に伝わり、より分かり易い期待スキル共有に繋がることを願っています。
(注) 1. データサイエンス協会の発行する「データサイエンティスト・スキルチェック・リスト」Ver.6 初版は、
以下のWebページから、Excelファイル形式でダウンロードできます。(2025年12月20日現在)
DSスキルチェック・リスト Ver.6

次回のテーマ予定:
「データを活用したモノ・コトの可視化」が意味すること
これまでのメッセージ --> こちら
新着情報(本年分)
- 2025年12月21日
- 所長メッセージ、更新しました(その158)。 (New)
- 2025年11月27日
- レポート2025-7の内容を更新しました。
- 2025年11月25日
- 所長メッセージ、更新しました(その157)。
- 2025年11月25日
- 「ひと味加えるオントロジー談義」資料(抜粋版)(レポート2025-7)登録しました。
- 2025年8月28日
- QUDTオントロジー(単位類標準化)の概要(抜粋)紹介(レポート2025-6)登録しました。
- 2025年7月31日
- 所長メッセージ、更新しました(その156)。
- 2025年7月25日
- ネットワーク・グラフとリレーショナル・モデル特性比較資料(レポート2025-5)登録しました。
- 2025年6月28日
- 所長メッセージ、更新しました(その155)。
- 2025年6月28日
- IOF サプライチェーン・オントロジー SCO2.0調査資料(レポート2025-4)登録しました。
- 2025年5月29日
- IOFにて展開する製造業オントロジーサプライチェーン領域適用例をレポート2025-03登録しました。
- 2025年5月26日
- 所長メッセージ、更新しました(その154)。
- 2025年4月27日
- 所長メッセージ、更新しました(その153)。
- 2025年3月27日
- 知識グラフ構築・活用の海外事例資料を元に作成した資料を、游悠レポート2025-02登録しました。
- 2025年2月25日
- 所長メッセージ、更新しました(その152)。
- 2025年1月25日
- 所長メッセージ、更新しました(その151)。
- 2025年1月24日
- ワイン・オントロジー探求シリーズの最終回として游悠レポート202501-Report登録しました。
- 2025年1月2日
- 所長メッセージ、更新しました(その150)。
- 2025年1月1日
- 【新年のご挨拶】謹賀新年、2025。さていよいよ、さまざまな視点、領域、人々から激動の年と議論する話題の多く想定される2024年の幕が開けました。乙巳の時代は新たな価値観を迎えつつも「再生と変化」が生まれ「着実な努力を通じ物事の安定に向けた行動が要求される時とも伝えられています。世界情勢、国内の社会、政治状況など予測を付け難い時代に加速がつく厳しい時を迎えようとしているようにも観ぜられます。近い時期に思わぬ出来事があろうとも、私たちは「トキトコロ」を見極めて対応してゆきたいものです
所長の立場としては、昨年に引き続き「ローカル&ユニバーサル視点に立つ」という思いを一層心に留め、邁進する年を迎えたいと考えています。今年のテーマは「意識の源泉をどう捉え、世界と向き合うか?」です。これまで、またこれからにおいてもご縁のある関係の皆様方と次の一年を過ごしてゆくことに致します。引き続き宜しくお願い致します。